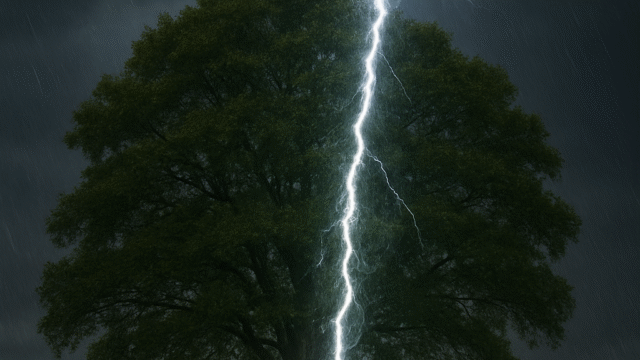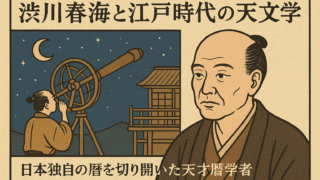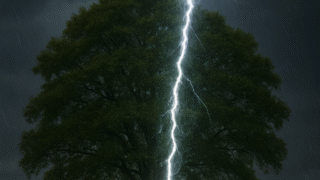私たちが空を見上げると、もくもくと浮かんでいる雲。
「水蒸気が集まってできる」とよく言われますが、実は水蒸気だけでは雲は生まれません。
雲ができる鍵を握っているのが “エアロゾル” です
この記事では、エアロゾルがどのように雲の誕生を促し、地球の気候にどんな影響を与えているのかを分かりやすく解説します。
そもそもエアロゾルとは?
エアロゾルとは、空気中に漂う微小な固体・液体の粒子 のこと。
例を挙げると…
-
ほこり
-
海から生じる塩の粒
-
黄砂
-
火山灰
-
工場や車の排ガス
-
煙、スス
-
花粉
-
ミスト状の水滴
大気は“透明”に見えて、実はこのような大量のエアロゾルが漂っています。
雲の材料は「水蒸気」と「エアロゾル」
雲は 水蒸気が凝結して生まれる ものですが、
意外にも“水蒸気同士”は勝手にくっついて水滴になりにくい性質があります。
そこで必要になるのが エアロゾル=凝結核(ぎょうけつかく) です。
◉ 雲ができる基本ステップ
-
空気が冷える
-
空気中の水蒸気が飽和状態になる
-
水蒸気がエアロゾルにくっつく
-
微小な“雲粒(うんりゅう)”が生まれる
-
雲粒がたくさん集まり、雲が見えるようになる
雲の元となる水滴は 髪の毛の100~1000分の1程度の小ささ。
肉眼では見えませんが、無数に集まると白く見えるようになります。
エアロゾルの種類によって雲が変わる?
雲を作るエアロゾルは 「雲凝結核(CCN)」 と呼ばれます。
このCCNの種類が変わると、雲の性質も変わります。
海塩粒子 → 大きい雲粒ができやすい
海から舞い上がる塩の粒は水と相性がよく、
比較的大きい雲粒が形成されます。
これは雨になりやすい雲です。
ススや汚染粒子 → 小さい雲粒が大量にできる
人間活動由来のエアロゾルは、雲粒を細かくバラバラに作ります。
その結果…
-
雨になりにくい
-
雲が長く残りやすい
-
日光を反射しやすい“白い雲”が増える
といった変化が起こります。
エアロゾルは気候変動にも影響している
雲は 太陽光を反射して地表を冷やす働き を持ちます。
エアロゾルの増減によって雲の性質が変わるため、結果として…
☀️地球が冷えやすくなる(エアロゾル増加時)
-
細かな雲粒 → 雲が白く、光を強く反射
-
雨になりにくい → 雲が長く残る
☁️逆に温暖化を促すケースもある
-
黒いエアロゾル(スス)が光を吸収して地表を加熱
-
上空の雲が赤外線を閉じ込める
このように、エアロゾルと雲の関係はとても複雑で、
現在も世界中で研究が続く重要なテーマです
まとめ:雲は“エアロゾルが作る自然のアート”
雲は、水蒸気だけでは生まれません。
空気中に漂う微細なエアロゾルが「核」になって初めて雲が形を作ります。
-
エアロゾルの増減 → 雲の形や性質が変わる
-
雲の変化 → 地球の気候に影響する
つまりエアロゾルは、
気象・環境・地球温暖化 と深くつながった非常に重要な存在と言えます。